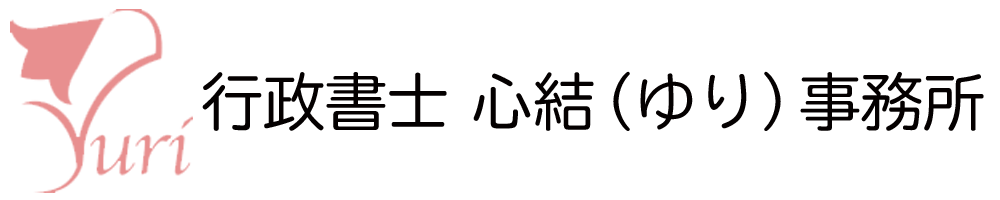就労ビザとは日本で働くために必要な在留資格です。
会社経営者や会社員、個人事業主として働くことが可能な在留資格を「就労ビザ」と呼びます。
日本で就職先が決まってから就労ビザを申請するという流れになります。
就労ビザでは、スーパーやコンビニのレジ打ち・工場のライン作業などの単純作業はできません。
就労ビザの種類
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能
- 企業内転勤
- 経営・管理
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 介護
- 興行
- 特定技能
- 技能実習
就労ビザの申請方法
就労ビザの申請方法は、新規申請と変更申請の2つがあります。
- 就労ビザの新規申請 (在留資格認定証明書交付申請)
- 在留資格の変更申請 (在留資格変更許可申請)
外国人の方の状況によって、手続きが異なります。
在留資格認定証明書交付申請
◇海外にいる外国人を雇用する場合は在留資格認定証明書交付申請の手続きが必要です。
日本国内で、申請人の家族又は受け入れ企業が、申請人の予定居住地または受け入れ企業の所在地を管轄する出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請します。
その後、交付された在留資格認定証明書を海外在住の申請人に送付します。
在外公館(海外にある日本大使館・領事館)で、申請人が在留資格認定証明書を添付してビザ(査証)を申請すると、スムーズにビザ(査証)が発給され、日本に入国することができます。
※在留資格認定証明書の有効期限は、3カ月です。
有効期限内にビザ(査証)の発給を受けて、日本に入国して下さい。
※在留資格認定証明書が交付されても、在外公館(海外にある日本大使館・領事館)でビザ(査証)が発給されないことがありますので、この点についてはご了承ください。
在留資格変更許可申請
◇日本に在留中の外国人が、現在持っている在留資格とは別の在留資格に変更する際には、在留資格変更許可申請の手続きが必要です。
留学生が日本で就職する場合や日本人配偶者と離婚又は死別したものの引き続き日本で生活したい場合など、在留資格に変更が生じるときには、在留資格変更許可申請をしなければなりません。
就労ビザの注意点
外国人の就労ビザ取得においては、外国人本人のみならず、企業も気をつけなければならないことがあります。
ルールを守っていないと、最悪の場合、罰則を科せられる恐れがありますので、注意が必要です。
①就労ビザの有効期間と更新方法
就労ビザには在留期間があります。更新を忘れて、在留期間を過ぎてしまうと、不法滞在になってしまうため、注意が必要です。在留期間が満了する前に更新申請を行い、許可が下りれば、日本で働き続けることができます。
更新申請は、在留期限の3か月前からできますので、早めの準備をおすすめします。
また、更新手続きの審査中に在留期限が過ぎてしまう場合がありますが、在留期限までに更新申請をした場合は、在留期限を過ぎても2か月間の特例期間が認められています。
②日本人と同等以上の給与であること
外国人だからという理由で、給与を下げることはできませんので注意してください。
会社内の、勤続年数、職務内容、年齢などが近い日本人と同等以上の給与でなければなりません。
③業務内容が入管法に適合すること
外国人が行うことができる業務の内容は、就労ビザの種類によって異なります。
外国人の業務内容が、入管法のそれぞれの就労ビザの基準に適合するかを確認してください。
入管法で認められていない活動を、報酬を得て行うと不法就労にあたり、企業が不法就労助長罪で罰せられる可能性があるので、注意が必要です。
④就労ビザを持つ外国人を雇用する際の手続き
外国人を雇用する際は、労働関係法規や、労災保険、社会保険、税務関係において、日本人と同じように適用されます。
日本人と同じように雇用管理を行う必要があります。
⑤3か月以上その活動をしていないと、取り消しの対象になります
退職した外国人は、3か月以上、その就労ビザの活動をしていないと在留資格の取り消し対象になります。
外国人が退職する際には、忘れずに伝えておきましょう。
また、退職後3か月以内に帰国するか再就職するのでない限り、外国人の就職活動は必須です。
まとめ
以上、就労ビザについて解説しました。
行政書士心結事務所(ゆりじむしょ)では、就労ビザをはじめ、各種ビザ申請のサポートをしております。
ビザの申請手続きについてお困りの方や、ご不安のある方は、お気軽に当事務所にご相談ください。